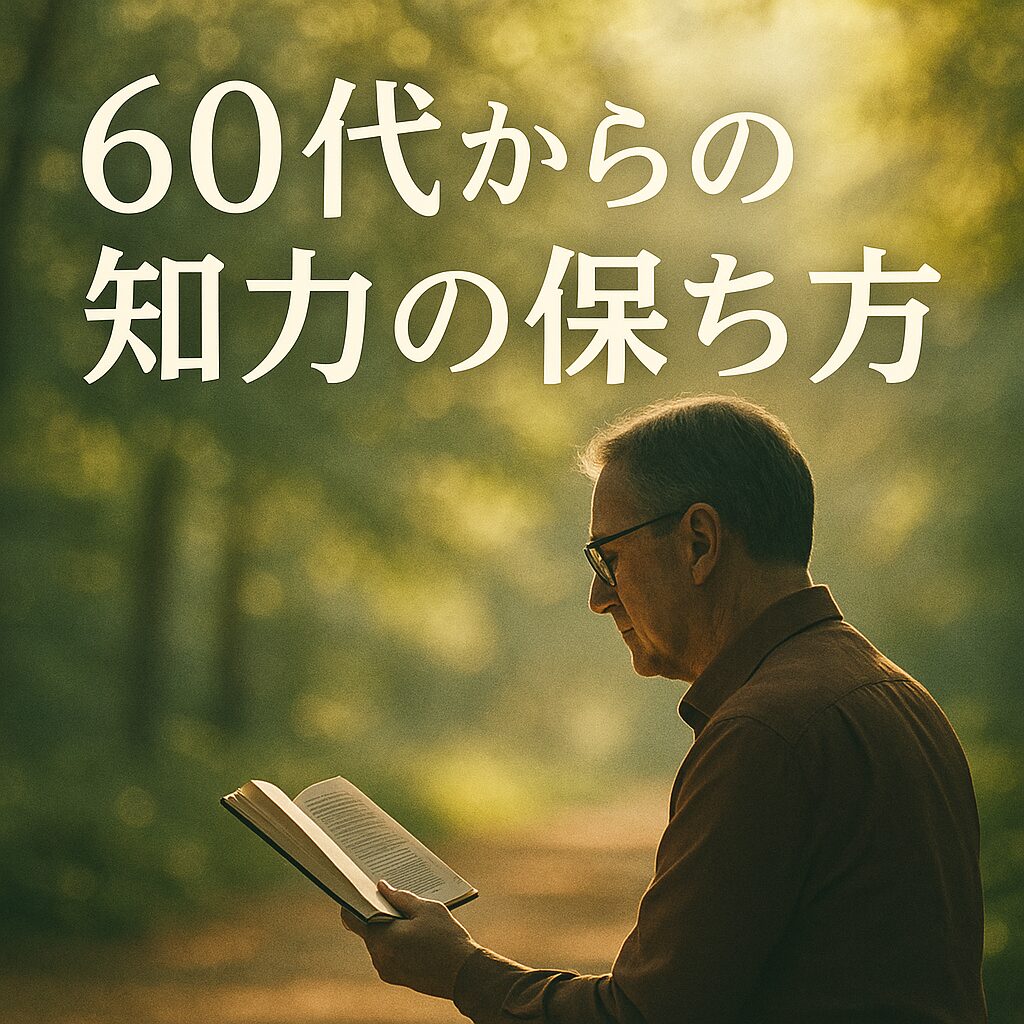はじめに:60代という節目に読むべき一冊
60代に入り、自分の知力や生き方について考える機会が増えた。
そうした中で出会ったのが、斎藤孝氏の著書『60代からの知力の保ち方』である。
本書は、知力を「生きる力」と定義し、それをどう保ち、鍛えていくかについて具体的な方法を示している。
本記事では、心に残った主なポイントとともに、60代をより充実して過ごすためのヒントを紹介する。
不安とどう向き合うか:「闘わない」という選択
歳を重ねるにつれて、「死」や「衰え」といった不安が現れてくる。
斎藤氏は、不安と闘うのではなく、「安らいだ感覚が湧き出る状況に身を置く」ことが大切だと説く。
本書では、論語や浄土宗の教えを例に、不安を受け入れながら生きるための思考法が紹介されている。
自分なりに納得できる言葉や考え方を持つことが、不安と上手く付き合う鍵となる。
とはいえ、不安は一度乗り越えたつもりでも、時間が経つと再び心を占めることがある。
その都度、信じられる考えに立ち戻り、静かにやり過ごす姿勢が求められるのである。
身体を整えることが、知力の基盤となる
知力とは、単に情報を記憶する能力ではない。
新たな知識を得て、理解し、応用する力、つまり深く思考する力である。
そのためには、身体の状態が整っていることが前提となる。
斎藤氏は「自然体」であることを重視している。
この言葉は多くの場面で耳にするが、本書を読んで改めてその意味に納得させられた。
無理をせず、自分のリズムを保ちながら心身を整えることが、知的活動の土台となるのだ。
文化に触れることが、知力と教養を育てる
文化は、私たちの生活において「知力」や「教養」として宿る。
それは長い歴史の中で積み重ねられた価値観や知識、思想の結晶であり、時に精神的な支えともなる。
文化に触れることによって、感性が育ち、視野が広がる。
そうして培われた知識や教養は、私たちの知力の一部として蓄積され、生きる力として働くのである。
おわりに:60代は知力を磨き直す好機
60代は、仕事や子育てに追われていた時期を越え、時間的にも精神的にも余裕が生まれる年代である。
その分、不安が入り込む余地もあるが、だからこそ、知力を鍛え直すには最適なタイミングでもある。
知力を保つことは、単なる脳の健康維持ではない。
それは、人生をより深く、豊かに味わうための力であり、精神的な充実をもたらす基盤となる。
本書は、そんな「知力=生きる力」の再発見を促す一冊であった。
同世代の方に、ぜひ手に取ってもらいたい。