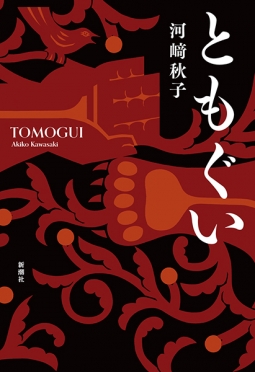【全体的な感想など】
直木賞受賞作。
本書題名の「ともぐい」とは、同類の動物の一方が他方を食うこと。
生きる営みの中での行動とはいえ、残酷さを感じるのだが、比喩的な意味として、仲間や同類の者が、それぞれ自分だけの利益を求めて他を害する結果になること、とある。
この意味において、人間の社会では、「ともぐい」が残酷、非情に行われると言えるのかもしれない。
命がかかった時、動物も人も本能のまま、本性むき出しで生きようとするであろう。
そして人は時に動物より狡くもあるのだが、
他者を助け、また思いやる心が持てるのも人ゆえである。
【あらすじ】
明治時代の北海道、厳しい自然とともに生きる一人の猟師・熊爪。
山に小屋を構え、獣を追い、解体し、その肉や毛皮で糧を得る日々。人里を離れ、自然と向き合う彼の暮らしは、過酷であると同時に、自立と誇りに満ちている。
町で商いを営む青年・良輔との偶然の出会いは、熊爪の人生に思いもよらぬ影響を与えていく。
それぞれ全く異なる世界に生きる二人が、時代のうねりの中で交差しながら、自分の生き方を問い直していく——。
自然と文明、人間と獣、孤独とつながり。
極限の世界で繰り広げられる壮絶な生と死のドラマが、読む者の胸に深く迫ります。
【まとめ】
熊爪の山で生きる力強さは、厳冬のマイナス30度の鹿猟の場面などから感じられた。
鹿を銃で仕留め、即、自らナイフで捌き、
その場で肝臓をナイフで切りながら食すのである。獲れれば食べるまで。
熊爪の狩猟生活から、人間は命を頂くことで生きているということを、見せつけられる。
多くの現代人の生活は、熊爪とはおよそかけ離れているが、人間も、動物も同じ生命として、他の命を取り入れることで生き続けられるという本質を理解しておくことは大切なのだと思う。